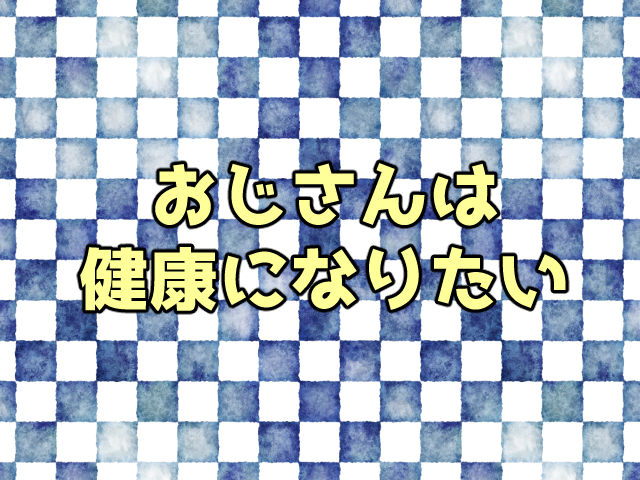林修の今でしょ!講座で、ミニ野菜のスゴさを学ぶ
ミニトマトや芽キャベツ、ヤングコーン、ミニキャロットなど、今では珍しくなくなってきたミニ野菜。
おべんとうやメインのおかずなどに、彩りを添えるものというイメージがありますが、実は、ミニ野菜自体にも健康長寿につながるすごいパワーを持っているのだそうです!
今回は、そんなミニ野菜のなかで、特にすばらしいパワーを持つトップ3について学びます。
<林修の今でしょ!講座>
テレビ朝日系列で放送されている教養バラエティ番組。
講師である林修が生徒となって、各界から講師を招いて授業を受ける。
▽▲▽▲▽
今回のポイント
私なりに今回注目するポイントは、
- 第1位 豆苗:骨を丈夫にするパワーが約6倍
- 第2位 芽キャベツ:胃腸を元気にするパワーが約4倍
- 第3位 ミニトマト:血管&肌を老けさせないパワーが約2.5倍
と、なります。
ミニ野菜と聞いて思いつくのは、ミニトマト、芽キャベツ、ヤングコーン、かいわれ大根にブロッコリースプラウトがすぐに思いつきました。
普段、なにげなく目にしているこれらのミニ野菜ですが、こんなにもすごい栄養素を持っているのには驚いてしまいますね!?
豆苗ってなんの芽?
私も知らなかったのですが、豆苗は、実はさやえんどうの芽なんです。
しかも、さやえんどうをさらに成長させたものが、グリンピース。
へぇ~、そうだったんですねぇ~!
▽▲▽▲▽
ミニトマト、リコピンのパワーで血管や肌を老けさせない!
まずは、第3位にランクインしたミニトマトからです。
トマトといえば赤、この赤さこそリコピンが豊富に含まれていることを示します。
そう、トマトといえばリコピン!!というのは、今では私でも知っている有名な栄養素です。
このリコピンが、トマトとミニトマト、それぞれ100gあたりに、約3mg、約8mg含まれているそうです。
つまり、ミニトマトの方が、約2.5倍のリコピンを含んでいることになります。(8割る3だから、約2.66倍?)
そして、リコピンは高い抗酸化作用を持つので、血中の悪玉コレステロールによる血管の酸化を抑える効果が期待でき、動脈硬化のリスクを減らす効果を得られます。
また、同じ理由で、肌のシミやシワの予防効果も期待できるとのこと。
美肌とアンチエイジングが期待できる、ホントにすごいですね、リコピンは!
なぜミニトマトにリコピンが多く含まれているのか?
普通のトマトより、ミニトマトの方が多くリコピンが含まれている理由は、実際にトマトとミニトマトを見る、というか、食べた時の触感を思い出すと分かるかもしれません。
以上を踏まえての問題です。
- ミニトマトにリコピンが多いのはなぜ?
- 普通のトマトに比べ皮が厚く、その皮にリコピンはく含まれるから
ミニトマトの方が皮が厚いためにリコピンが多いのですが、さらに大きさも関係があります。
同じ重さで考えた場合、直径が小さい方が表面積も広くなります。
ということは、皮の面積も広いということなので、リコピンも多くなるのです。
ミニトマトの栄養素を無駄にしない食べ方
ちなみに、ミニトマト農家の皆さんの血管年齢を測定してみると、軒並み実年齢よりも若い結果でした。
なかには-30歳と、非常に優秀な方も!?
そんな農家の皆さんは、ミニトマトのリコピンを効率よく吸収できる食べ方もしていました。
ということで、2問目の問題です。
- リコピンの吸収率をUPさせるミニトマトの食べ方とは?温めて食べるる?冷やして食べる?
- 温めて食べる
ミニトマトは熱を加えると皮も柔らかくなり、細胞が壊れやすくなるため、細胞内にあるリコピンが吸収しやすくなる
栄養素の吸収率を高める方法として、栄養素が入っている細胞を壊すというのは、よく聞く理由です。
農家の皆さんは、トマトのツミレ汁なるものを食べているそうで、まさに理にかなっている食べ方なんですね。
ということで、トマトよりもミニトマトを、吸収効率のよい食べ方をして、沢山リコピンを摂取し、血管は肌の老化対策を行いましょう!
芽キャベツのビタミンACEで、胃腸を元気に!
すごいミニ野菜、第2位に選ばれたのは、芽キャベツでした。
正直、芽キャベツはほとんど食べたことがありません。
そんな私にとって馴染みのない芽キャベツなんですが、キャベツに比べてビタミンが豊富に含まれているとのこと。
普段の食事でビタミンが不足しているのではと感じている私にとって、もしかしたらとても有用なミニ野菜なのかもしれません。
ビタミンCの場合、100g中にキャベツが約41mgなのに対し、芽キャベツは約160mgと約4倍も含まれているらしいです。
しかも、ビタミンAやEに至っては、それ以上の差が!?
- ビタミンAは、約14倍
- ビタミンCは、約4倍
- ビタミンEは、約6倍
芽キャベツは、キャベツに比べてこれだけ多くのビタミンを含んでいるらしいのです。
(なぜビタミンAの約14倍を例にして紹介しなかったのか・・・、割合表記だから、何かしらのトリックあり?具体的数値を出すと少なすぎるのかな?)
とにかく、少なくともキャベツより芽キャベツの方がビタミンA、C、Eが多いのは確かなようです。
3つ合わせてビタミンACE、胃腸を守るパワーもUP!
ビタミンA、C、Eには、胃腸に対して以下の効果が期待できるそうです。
- ビタミンA:胃の粘膜を保護する
- ビタミンC:抗酸化作用が強く、活性酸素の活動を抑える
- ビタミンE:胃腸の細胞膜の酸化を防止
どれも胃腸を守る心強いビタミンですが、これらをまとめてビタミンACEと番組では呼称(笑)。
そして、芽キャベツは、このビタミンACEをまとめて摂取できる非常に便利なミニ野菜ということになります。
ちなみに、ビタミンCの1日の摂取目安は100gmなので、キャベツなら1/4個となり、ちょっと食べるのは大変です。
ですが、芽キャベツの場合だと5個くらい食べればよいので、キャベツに比べたら一気に食べやすくなります。
逆流性食道炎を治療中でもあるので、胃の粘膜保護に効果が期待できるなら、積極的に食べるようにしようと思うのでした!
芽キャベツの栄養素を無駄にしない食べ方
芽キャベツにビタミンが豊富な秘密は、ミニトマトと同じく、キャベツと芽キャベツを見比べると、その違いから理由が分かるそうです。
小さな芽キャベツなので、緑の部分の割合がキャベツに比べて少ない、つまり白い芯の部分の割合が多いといことになります。
そして、その芯の部分にこそビタミンが多く含まれているため、同じ重さなら芽キャベツの方がビタミンを多く含んでいることになるのだそうです。
さらに、キャベツの芯は硬くて食べにくいので捨ててしまいがちです。
でも芽キャベツなら丸ごと食べることができるので、ビタミンを無駄にせず摂取することができます。
また、胃腸を元気にする理にかなった食べ方として、芽キャベツのシチューが紹介されていました。
- 芽キャベツ(抗酸化)×肉&牛乳(タンパク質)
タンパク質が胃の粘膜の材料となるので、この食べ合わせが胃腸を元気にしてくれるのだそうです。
ということで、芽キャベツは、タンパク質と一緒に、芯まで食べるのが、栄養素を無駄にせず、胃腸を元気してくれる食べ方となります。
芽キャベツが大きく成長すると、普通のキャベツになるのか?
答えは、否です。
キャベツと芽キャベツは、どちらも品種改良されて作られた別の品種なんだとか。
芽キャベツは、茎の部分を覆うように沢山の芽キャベツが生えるようにでき、キャベツとは育ち方がぜんぜん違います。
▽▲▽▲▽
豆苗、健康長寿につながる最強のミニ野菜
そして、第1位が、豆苗です。
こちらも個人的には馴染みのないミニ野菜です・・・
健康長寿に大事なこと、それは骨が丈夫なことです。
ちょっとしたことで骨折をしてしまうと、そのまま寝たきりになってしまうリスクが高くなってしまうから。
ちょっとやそっとでは折れない丈夫な骨こそが、健康長寿の基本だと思います。
そんな骨を丈夫にするのに必要な栄養素といえば、まっさきにカルシウムを思い出されますが、実はカルシウムだけだと不十分らしいのです。
骨を丈夫にするにはビタミンKも必要で、そのビタミンKを豆苗が多く含んでいるのだそうです。
豆苗は、さやえんどうの赤ちゃんですが、同じ100g中に含まれるビタミンKは、さやえんどうの約47μg(マイクログラム)に対し、豆苗は約280μgと約6倍も多いとのこと。
ちなみに、1μg=1/1000mgです。
ビタミンKは、どういうふうに骨によいのか?
骨は一定量のカルシウムの出入りなどにより、常に新しく作りかえられており、また、骨はカルシウムだけでできているわけではないのだそうです。
骨の2/3はカルシウムですが、カルシウムだけだとちょっとした衝撃で折れやすくなるので、骨にしなやかさを持たせるために1/3はコラーゲンからできています。
骨のしなやかさ=タンパク質(コラーゲン)
そこで、ビタミンKが重要になります。
ビタミンKは、カルシウムやタンパク質(コラーゲン)の吸収をUPさせ、骨の形成を促すとても大事な効果が期待できるのです。
そのため、ビタミンKはカルシウムやタンパク質(コラーゲン)と一緒にとるのが重要になります。
豆苗の栄養素を無駄にしない食べ方
1日に摂取すべきビタミンKは、成人で150μgらしいのですが、さやえんどうで摂取しようとすると約300g必要と、食べ切るにはちょっと多いかなと。
でも、豆苗なら約70gに相当するので、炒め物などに入れればペロッと食べられる量になります。
また、ビタミンKはカルシウムやタンパク質(コラーゲン)と一緒にとるのが良いので、骨を強くするパワーUPの豆苗の食べ合わせは、
- 豆苗×チーズ
- 豆苗×鶏肉
が紹介されていました。
豆苗と一緒に食べることで、チーズはカルシウムが豊富なのでカルシウム吸収率UP、鶏肉には良質なタンパク質が含まれているのでタンパク質吸収率UPの効果が期待できるという訳です。
また、豆苗はビタミンKだけではなく、以下のように他の栄養素も豊富に含まれているそうです。
| さやえんどう | 豆苗 | |
|---|---|---|
| ビタミンA | 約47mg | 約250mg |
| ビタミンE | 約0.9mg | 約3.5mg |
| β-カロテン | 約560μg | 約3000μg |
ビタミンAとビタミンEの効果は、芽キャベツで出てきました。
β-カロテンは免疫力を高めてくれる効果があるとのことです。
さて、豆苗最後の問題です。
- 豆苗は、赤ちゃんだから大人のさやえんどうより多い成分はなに?
- 苦味成分
まだ実になっていないため、食べられないために苦味成分が多く、この苦味成分は抗酸化成分
抗酸化成分は、豆苗が食べられたり、枯れたりしないよう、動物や紫外線から身を守るものです。
私たちにとっての抗酸化成分は、血管や肌の老化の原因となる活性酸素を抑制してくれる非常に嬉しい効果が期待できます。
豆苗に限らず、植物の赤ちゃんは同じ様にして身を守っています。
なので、いろいろな野菜の赤ちゃんであるミニ野菜は、私たちにとってありがたい栄養成分を含んでいるといえます。
ミニ野菜、見た目は可愛いですが、非常にすごい可能性を秘めていることが今回の番組で分かりました。
これからは、ミニ野菜にも注目して、いろいろ買ってみたいと思うようになりました。
おまけ、花粉症対策に効果的なミニ野菜
花粉症対策が期待されているスルフォラファン。
まだ研究段階のようですが、そのスルフォラファンを含むミニ野菜が、ブロッコリースプラウトです。
花粉症に限らず、スルフォラファンは免疫細胞のバランスをとり、アレルギー症状や炎症にも効果を期待されているとか。
そのスルフォラファンですが、成長してブロッコリーになると、ほとんど含まれなくなってしまうそうです。
花粉症ぽい症状がでることがあるので、少しでも抑えられるよう、ブロッコリースプラウトも食べる習慣をつけたいなと思いました!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
▲▽▲
▼△▼